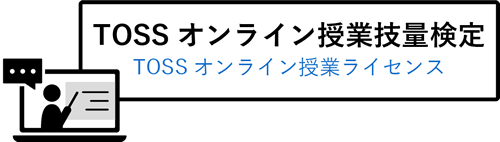審査員の規定(2022.9.27)
【1】審査員は、結果と内容を説明し、必要があれば代案を実演する。
複数の審査員での検定の場合、それぞれ採点し平均点を出す。審査員は挑戦者ごとに「目合わせ」を行う。ライセンス審査の結果と講評は、全ての挑戦者が受検し終わってから参加者全員に発表する。点数及び該当級は、必ず受検者に公表する。指定された授業時間を2パーセント以上オーバーしたら、評定外とする。例えば、3分の場合は4秒以上、5分の授業は6秒以上、オーバーしたら評定外とする。
【2】「飛び級」(2025.4.1改定)
1 「飛び級は原則として認めない」ことを基本とする。
ただし、「例外的に極めて優れた授業」の場合、以下のように飛び級を認める場合がある。
1.1 E・F表→優れた授業の場合、現地審査員の判断で2つまたは3つまでの飛び級を認める場合がある。(例:35級→32級)
1.1.1. E表からD表への表代わりの「初受検」で優れた授業の場合にも、2つまたは3つまでの飛び級を認める場合がある。
1.1.2. それ以上の飛び級は、例外なく一切認めない。
1.2. D表→非常に優れた授業の場合、現地審査員の判断で2つまでの飛び級を認める場合がある。
(例:27級→25級) それ以上の飛び級は、例外なく一切認めない。
1.3.ただし、現地審査員は明確な理由(注1)を検定事務局に報告する必要がある。
1.3.1. 理由を報告しなかった場合は飛び級を認めず点数はそのままで1つだけの昇級とする。
1.3.2. それ以上の飛び級は、例外なく一切認めない
(注1)その授業のどのような点がどのように非常に優れているのかを、具体的・描写的に記述すること
※2025年4月1日以前に受検し認定した場合は、以下の旧規定に従って「飛び級審査」を申請してください
飛び級で昇級の更新報告をする場合には、次の内容を事務局に送る。
1)受検者の指導案
2)当日の受検者の授業映像
3)当日の審査員の審査映像
4)「飛び級」になった理由の報告文
5)当日の審査表
上記の内容が送られてない場合、また送られても適切ではないと事務局が判断する場合には、飛び級を認めない。
ただし、F表E表D表受検の場合は次のようにする。
1)F表受検、E表、及びD表「初」受検の場合は、「飛び級」の規定は適用されない。
2)D表「初」受検の場合には、原則として「30級〜27級」の範囲で認定される。
3)その後は「飛び級」は原則として認めない。
【3】正式な検定を受けなくてもサークルでの模擬授業により無条件で級に認定される場合がある。
その基準は、サークル内で11回オンライン模擬授業→33級。8回→34級。5回→35級とする。ただし実際に受検する場合は、「F表からの受検」を行うこととする。
【4】審査員が、受検者の指導案や授業を事前に一度でも検討(コメント・代案等)した場合、その受検者の検定はできない。
【5】検定結果が前回の級より「下がった場合」は、「下がった検定結果の得点はそのまま」報告、「級」は「現在のもの(下がった級)」を報告し「現級留置」として申請する。級は下がらず「現級留置」として記される。